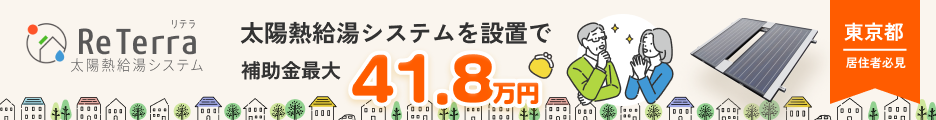column お役立ちコラム
【お金を貯める】50代・60代の最終調整!年金を見据えた出口戦略
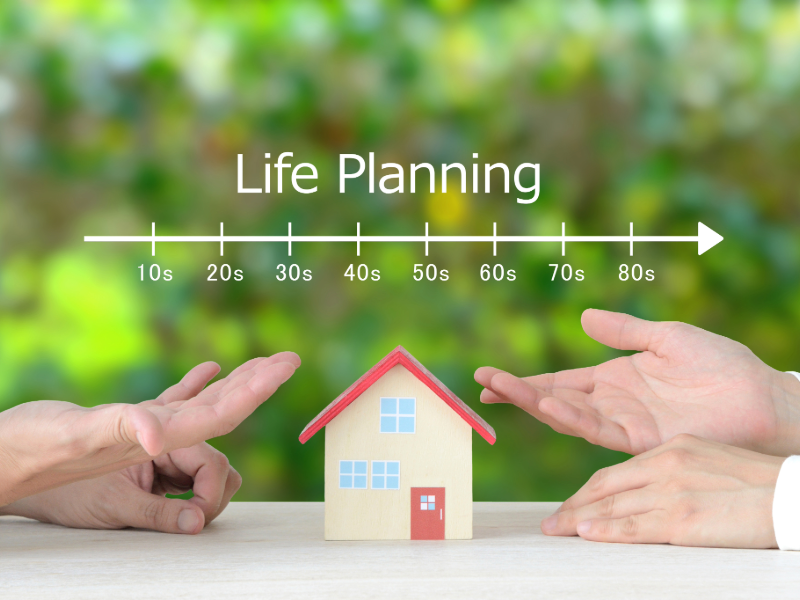
守りと攻めを切り替える最終ステージ
50代後半から60代に差し掛かると、お金との向き合い方は大きな転換期を迎えます。
これまでは「いかに資産を増やすか」が目標でしたが、この時期からは「蓄えた資産をいかに効率よく長持ちさせるか」へとシフトする必要があります。
人生100年時代といわれる今、退職後の生活は30年以上続く可能性があります。
年金収入だけでは不足する生活費を、手持ちの資産でどう補っていくのか。この「出口戦略」こそが、豊かな老後生活を実現するための最重要課題なのです。
この時期の節約目標は、単なる支出削減ではありません。資産を効率よく『長寿命化』させ、人生の最終ステージを安心して楽しむための土台づくりです。
本記事では、年金生活を見据えた固定費の最終見直しと、資産を賢く取り崩すための具体的な戦略をご紹介します。これまで培ってきた資産を、最大限に活かすための設計図を一緒に描いていきましょう。
「守りの節約」:年金生活を見据えた固定費の究極の見直し
退職後は収入が現役時代の5〜6割程度に減少するのが一般的です。この現実を見据え、年金生活が始まる前に固定費を徹底的に見直しておくことが重要です。特に以下の3つの項目は、大きな削減効果が期待できます。
保険:死亡保障をゼロベースで見直す

子どもが独立し、住宅ローンも完済に近づいたこの時期、高額な死亡保障は本当に必要でしょうか?
見直しのポイント:
- 死亡保険の大幅削減: 子育て期に必要だった数千万円の死亡保障は、もはや不要です。残すべきは葬儀費用や配偶者の当面の生活費として200〜300万円程度で十分でしょう。
- 医療保険は公的制度を前提に: 高額療養費制度により、医療費の自己負担は月額約9万円(70歳未満・一般所得者)が上限です。預貯金で対応できるなら、月々の保険料負担を続ける必要性は低いといえます。
- がん保険の再検討: すでに加入から長期間経過している場合、保障内容が古く、保険料も割高になっている可能性があります。最新の治療実態に合った保障内容か確認しましょう。
削減例: 夫婦で月3万円の保険料を払っている場合、必要最小限に見直すことで月1万円程度に削減できるケースも。年間24万円、10年で240万円の差になります。
住居費:ライフスタイルの変化に合わせた選択肢

住居費は固定費の中で最も大きな割合を占めます。子どもの独立後、広すぎる家に住み続けることは、経済的にも管理面でも負担になります。
検討すべき選択肢:
- ダウンサイジング: 一戸建てから利便性の高いマンションへの住み替え、または賃貸への移行により、固定資産税や管理費、光熱費を削減できます。売却益を老後資金に充てることも可能です。
- リバースモーゲージの活用: 自宅を担保に融資を受け、死亡時に一括返済する制度です。住み慣れた家に住み続けながら、生活資金を確保できます。ただし、金利負担や相続への影響を十分に検討する必要があります。
- リフォームの最適化: 住み続ける場合でも、将来のバリアフリー化を見据え、計画的にリフォームすることで、無駄な出費を防げます。
移動費:車の維持費をゼロにする検討

車の維持費は、駐車場代、保険料、税金、車検代を合わせると年間30〜50万円にのぼります。利用頻度が減っているなら、思い切った見直しを。
削減のアプローチ:
- カーシェア・レンタカーへの切り替え: 月に数回程度の利用なら、必要な時だけ借りる方が圧倒的に経済的です。月2万円(年24万円)の駐車場代だけでも削減できれば大きな効果です。
- 軽自動車・コンパクトカーへの乗り換え: 車を手放せない地域でも、維持費の安い車種に変更するだけで年間10〜20万円の削減が可能です。
- 免許返納後の生活設計: 将来的な免許返納も視野に入れ、公共交通機関やタクシーを活用する生活スタイルへの移行を検討しましょう。自治体によっては返納者への支援制度もあります。
「攻めの戦略」:資産を『長寿命化』させる出口戦略
固定費の見直しで支出をスリム化したら、次は蓄えた資産を賢く活用する「出口戦略」に取り組みましょう。税制優遇を最大限に活かすことが、資産を長持ちさせる鍵となります。
iDeCo・企業型DCの賢い受け取り方
60歳以降に受け取れるiDeCoや企業型DC。受け取り方によって税負担が大きく変わります。
受け取り方法の比較:
- 一時金受け取り: 退職所得控除(勤続20年超なら「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」)が適用され、税負担が軽くなります。さらに課税対象額は1/2に圧縮されます。
- 年金受け取り: 公的年金等控除(65歳以上なら最低110万円)が適用されますが、他の年金収入と合算されるため、税負担が増える可能性があります。
- 併用パターン: 一部を一時金、残りを年金で受け取ることで、両方の控除枠を活用する方法もあります。
重要なポイント: 退職金や企業年金との兼ね合い、他の収入状況によって最適解は異なります。
受け取り開始の1〜2年前にファイナンシャルプランナーへの相談を強くお勧めします。試算せずに受け取ると、数十万円単位で損をする可能性があります。
公的年金の「繰り下げ受給」を検討する

公的年金は原則65歳から受給開始ですが、受給開始を遅らせることで年金額を増やせます。
繰り下げ受給のメリット:
- 増額率: 1か月遅らせるごとに0.7%増額。70歳まで繰り下げると42%増、75歳まで繰り下げると最大84%増になります。
- 生涯受給総額: 健康で長生きする自信があるなら、繰り下げた方が生涯受給総額が増える可能性が高まります。損益分岐点は概ね12年後です(例:70歳受給開始なら82歳)。
判断のポイント:
- 65歳から受給開始までの生活費: 預貯金や退職金、継続雇用での収入で賄えるか?
- 健康状態: 家族の健康歴や自身の健康状態を考慮しましょう。
- 配偶者の年金: 夫婦で戦略を立てることも重要です。例えば「夫は繰り下げ、妻は65歳受給」など。
注意点: 繰り下げ待機中に障害年金や遺族年金を受給すると、繰り下げができなくなります。また、加給年金は繰り下げ期間中は支給停止されます。
新NISAを「取り崩し」の器として活用する

2024年から始まった新NISA制度は、老後の資産取り崩しにおいても強力なツールです。
NISAを取り崩しに活用するメリット:
- 売却益が非課税: 通常の課税口座では売却益に約20%の税金がかかりますが、NISA口座なら非課税です。例えば100万円の利益が出た場合、約20万円の節税効果があります。
- 配当・分配金も非課税: 保有し続けることで得られる配当も非課税で受け取れます。
- 柔軟な取り崩し: 必要な時に必要な額だけ売却できます。年金受給額や支出に応じて調整可能です。
取り崩し戦略の例:
- 定額取り崩し: 毎年一定額(例:年120万円=月10万円)を取り崩す方法。シンプルで管理しやすい。
- 定率取り崩し: 資産残高の一定割合(例:4%)を取り崩す方法。資産の長持ちを重視する戦略。
- 公的年金補完型: 年金だけで不足する分をNISAから補う方法。支出の変動に対応しやすい。
運用商品の選び方: 取り崩しフェーズでは、値動きの激しい個別株よりも、分散されたインデックスファンドやバランスファンドが適しています。安定的なリターンを重視しましょう。
まとめ:節約から「人生を楽しむための資金計画」へ

50代・60代の資産管理は、単なる節約術ではありません。人生100年時代を安心して、そして豊かに生きるための「設計図づくり」なのです。
この時期に取り組むべきことは:
- 固定費の最終見直しで年金生活の基盤を固める
- 税制優遇を最大活用して資産を効率的に取り崩す
- 年金戦略を練り直すことで生涯収入を最大化する
これらの戦略は、決して難しいものではありません。一つずつ着実に実行していくことで、「老後資金が足りるだろうか」という不安は、「これだけ準備できた」という安心感に変わっていきます。
資産を長持ちさせる目的は、ただ長生きするためではありません。趣味を楽しみ、旅行に出かけ、時には贅沢をする。そんな豊かな時間を、経済的な心配なく過ごすためです。
これで、全世代共通編から50代・60代編まで、節約術のコラムシリーズが完結しました。
各世代に応じた戦略を実践し、それぞれのライフステージで充実した人生を送っていただければ幸いです。
まずはできることから、一歩ずつ。あなたの理想の老後生活に向けて、今日から出口戦略をスタートさせましょう。
▼ReTerraをお得に導入するならこちらをチェック!