column お役立ちコラム
【お金を貯める】30代・40代必見! 複雑な家族家計を最適化する戦略

支出の「ピーク期」を乗り越えるための家計戦略
30代・40代は、人生で最も家計が複雑になる時期です。
住宅ローンの返済が始まり、子どもの教育費が増え、さらには老後資金の準備も視野に入れなければならない──この3つの大きな支出が同時に押し寄せる「家計のピーク期」を、多くの方が経験しています。
ある調査によれば、30代後半から40代前半の世帯では、住宅関連費、教育費、保険料だけで収入の40〜50%を占めるケースも珍しくありません。
毎月の収支がギリギリで、貯蓄に回す余裕がないと感じている方も多いのではないでしょうか。
しかし、この時期の節約は単なる「我慢」ではありません。
必要なのは、無駄を削る「守り」と、将来を見据えた資金計画を立てる「攻め」の両輪です。この2つのアプローチを組み合わせることで、複雑な家計も必ずコントロール可能になります。
今回は、30代・40代の家計に潜む「見えない無駄」を徹底的に洗い出し、夫婦で協力して家計を最適化する具体的な戦略をご紹介します。
「守り」の最適化:大きな支出の無駄を徹底排除

保険の「二重取り」を見直す
住宅ローンを組む際、ほとんどの方が「団体信用生命保険(団信)」に加入します。これは、契約者が死亡または高度障害状態になった場合、住宅ローンの残債がゼロになる保険です。
ここで見落とされがちなのが、既存の生命保険との重複です。住宅購入前に加入した生命保険の死亡保障額が、住宅ローン残債と同等かそれ以上の金額になっている場合、実質的に「二重取り」の状態になっています。
例えば、3,000万円の住宅ローンを組み、団信に加入している方が、別途3,000万円の死亡保障がある生命保険に入り続けているケースを考えてみましょう。
万が一のことがあった場合、団信でローンはゼロになり、さらに生命保険から3,000万円が支払われます。遺族の生活費として必要な額を超えている可能性が高いでしょう。
見直しのポイント:
- 住宅購入前に加入した生命保険の保障内容を確認
- 団信でカバーされる住宅費用分を差し引いた、本当に必要な保障額を計算
- 保障額を減額または保険を見直すことで、月々数千円〜1万円以上の節約が可能
ある40代の家庭では、この見直しだけで月額8,000円、年間約10万円の削減に成功しています。10年間で100万円以上の差になります。
住宅ローンは「借り換え」を検討

住宅ローンは人生最大の借金です。
金利のわずかな差が、総返済額に驚くほど大きな影響を与えます。
例えば、残債3,000万円、残り期間25年、現在の金利1.5%のローンを、金利0.9%に借り換えた場合を考えてみましょう。
- 借り換え前: 月々約12万円 総返済額約3,600万円
- 借り換え後::月々約11.2万円 総返済額約3,360万円
この場合、総返済額で約240万円もの差が生まれます。
月々8,000円の削減は小さく見えても、長期で見れば家族旅行数回分以上の節約になるのです。
借り換えを検討すべきケース:
- 現在の金利が1.0%以上
- ローン残高が1,000万円以上
- 残りの返済期間が10年以上
ただし、借り換えには諸費用(30万〜80万円程度)がかかります。
各金融機関が提供する借り換えシミュレーターを使い、諸費用を含めても総返済額が減るかを必ず確認しましょう。
最近では、借り換え相談を無料で行ってくれるサービスも増えています。
固定費は「サブスク」と「通信」にメスを入れる
子どもの成長に伴い、気づけば増えているのが動画配信サービスなどのサブスクリプション費用です。
Netflix、Amazon Prime、Disney+、各種音楽配信サービス……
家族それぞれが使うサービスを合計すると、月々数千円になっていることも珍しくありません。

サブスク見直しの3ステップ:
- 全サービスをリストアップ – クレジットカード明細を3ヶ月分確認し、定期的な支払いをすべて洗い出す
- 利用頻度を家族で共有 – 月に1回も使っていないサービスは即解約の候補
- 重複機能を統合 – 動画サービスは1〜2つに絞り、家族でアカウント共有
また、通信費の見直しも効果的です。
大手キャリアから格安SIMに変更するだけで、家族4人で月々1万円以上の節約になるケースもあります。最近の格安SIMは通信品質も向上しており、日常使いで不便を感じることは少なくなっています。
ある家庭では、サブスクの整理と格安SIMへの変更で、月々15,000円、年間18万円の固定費削減に成功しています。
この金額を10年間投資に回せば、将来的に大きな資産形成につながります。
「攻め」の資金計画:目的別口座と教育費の聖域化
守りの最適化で無駄を削ったら、次は「攻め」の資金計画です。
特に重要なのが、目的別に資金を管理し、教育費を「聖域」として確保する仕組みづくりです。
教育費の「聖域」を作る

教育費は、子どもの将来に直結する重要な支出です。
しかし、普段使いの口座に貯めていると、急な出費や生活費の不足でつい手をつけてしまいがちです。
教育費聖域化の具体的方法:
- 児童手当は全額別口座へ:支給されたら即座に教育費専用口座に移動。月々1万〜1.5万円×15年で200万円以上貯まります
- 自動積立を設定:給与振込後、自動的に教育費口座へ送金される仕組みを作る。「余ったら貯める」では絶対に貯まりません
- 教育費口座からは絶対に引き出さない:この口座は「存在しないもの」として扱い、緊急時でも手をつけない覚悟を
多くの金融機関では、1つの口座内で「目的別貯金」ができる機能を提供しています。
メイン口座とは別に、「大学進学費用」「塾・習い事費用」など、目的ごとに資金を分けて管理できます。
教育費の目安と準備戦略
文部科学省の調査によれば、幼稚園から大学まで、すべて公立に通った場合でも約800万円、すべて私立なら2,000万円以上が必要とされています。
年齢別・教育費準備の目安:
- 0〜6歳(未就学期): 月2万円の積立開始。児童手当を全額貯蓄すれば約7年で150万円以上
- 7〜12歳(小学生期): 月3万円に増額。学資保険や積立NISAの活用も検討
- 13〜15歳(中学生期): 高校受験費用として別途50万円を確保
- 16〜18歳(高校生期): 大学進学に向けて最終加速。月5万円貯蓄できれば3年で180万円
早く始めるほど、月々の負担は軽くなります。
30代前半から始めれば無理なく準備できますが、40代からでも遅くはありません。重要なのは「今日から始めること」です。
夫婦での「家計会議」を仕組み化

家計管理でよくある問題が、夫婦間の情報格差です。
「夫(または妻)が家計を握っていて、もう一方は詳細を知らない」という状態では、協力して節約することも、将来の計画を立てることもできません。
効果的な家計会議の方法:
- 定例化する – 毎月第1土曜日の夕食後など、日時を固定。30分でも十分です
- 共有すべき3つの数字
- 先月の収支(収入・支出・貯蓄額)
- 各目的別口座の残高(教育費、老後資金、緊急予備費など)
- 今月の予算と大きな出費予定
- 責めない、感謝する – 支出を責めるのではなく、「家計を一緒に考えてくれてありがとう」という姿勢で
- 家計簿アプリを活用 – マネーフォワードME、Zaimなどの家計簿アプリを夫婦で共有すれば、いつでもリアルタイムで家計状況を確認できます
ある夫婦は、月1回の家計会議を始めてから、年間の貯蓄額が50万円から120万円に増えたそうです。
「お互いが家計を意識するようになった」ことが最大の効果だったと言います。
老後資金の準備も忘れずに
30代・40代は教育費が優先されがちですが、老後資金の準備も並行して進めることが重要です。
特に、iDeCo(個人型確定拠出年金)や新NISAなどの税制優遇制度は、早く始めるほど複利効果で資産が大きく育ちます。
30代・40代の老後資金準備の基本:
- iDeCoで月々1〜2万円(所得控除で実質負担は減少)
- 新NISAで月々1〜3万円(つみたて投資枠を活用)
- 50代以降に備え、今のうちに投資経験を積んでおく
教育費と老後資金、両方を同時に貯めるのは大変ですが、守りの最適化で削減した固定費を、こうした「攻めの貯蓄」に回すことで、無理なく両立できます。
複雑な家計も仕組み化すれば必ずコントロール可能

30代・40代は、住宅ローン、教育費、老後資金という3つの大きな支出が重なる「家計のピーク期」です。
しかし、この時期を乗り越える鍵は、複雑さに圧倒されるのではなく、仕組みを作ることにあります。
今日から始められる3つのアクション:
- 保険と住宅ローンの見直し – 団信との重複チェック、借り換えシミュレーションを今週中に実施
- 教育費専用口座の開設 – 児童手当や教育費積立を完全に分離管理
- 家計会議の日程を決める – 来月の第1土曜日など、具体的な日時を夫婦で共有
複雑な家計も、夫婦で協力し、一つひとつ丁寧に仕組みを作れば、必ずコントロール可能になります。
今回ご紹介した「守り」と「攻め」の両輪を意識しながら、あなたの家庭に合った最適な家計戦略を見つけてください。
▼ReTerraをお得に導入するならこちらをチェック!
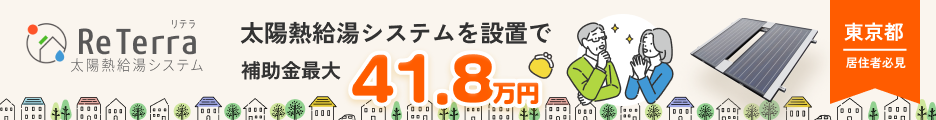
次回予告: いよいよ最終調整! 【50代・60代の節約術】では、年金と資産の取り崩し戦略を解説します。リタイア後も安心して暮らせる、賢いお金の使い方をお伝えします。







